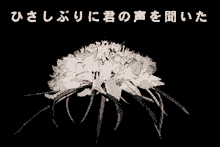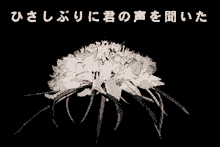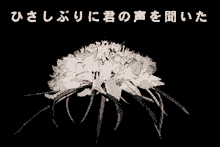
八戒は石の前に、そのへんの庭先で勝手に折ってきたツツジの枝を立て、メシを食う時のように勢いよくパンと手を合わせた。
「おひさしぶりです」
石。
俺には石としか言いようがないが、一応八戒の姉の墓である。
下に遺体も骨もないものを何が墓なのかよく分からんが、何もないというのもあれだろうと三蔵が寺院所有の土地にそれっぽい石を立てそれっぽい文字を刻んでくださったのだ。相変わらず悟能関係のことについちゃフォローが細やかな三蔵だ。
まあ、墓なんて生きてる奴の為のものだから。
「この方が悟浄さん。今、一緒に暮らしてます」
八戒は実に何年ぶりかで俺を「さん」付けした。俺は吹き出しかけてなんとか堪え、神妙に頭を下げた。
「どうも」
「どうもじゃないでしょう。初対面の女性に対して」
「知らねえもん!」
「僕の姉です。美人です。充分でしょう」
「…生きてるうちに一発お願いしたかったです」
殴られるかと思ったら、八戒は微妙に誇らしげであった。何発やったのか知らないがそこで誇れるとは結構な純愛だ。
俺と八戒が天気の良い昼下がりに彼女の墓参りに来たのは、もうすぐ旅に出るからという美しい理由ではない。八戒は八戒になってからここに来たことは一度もなかった。哀しくてももう済んだことだし、彼女の魂がここにいる道理もないという真っ当な理由で。今日八戒をここに連れてきたのは俺だ。
俺は彼女と初対面ではない。何度も会った。
何度も何度も話し合った。
威勢のいい女で、同い年である俺にも颯爽と上からものを言った。俺はそういう扱いはわりと好きなので、彼女の態度は好ましかった。
「可愛いでしょ、俺。よく言われるんだけど」
「そうねー。あと10年はそのキャラで誤魔化せるかもね」
こんなに近くにいて、お互い理解もしあっているのに、助け合うことができない。
どうしてもできない。
それは哀しいことだった。こんなに哀しいことはなかった。彼女は俺の頭を優しく撫でた。
「可哀想ね。私たち」
そして昨日、もうこれ以上話し合っても仕方がないから八戒に任せようということになった。
そんなことはお互い最初から分かっていたことだったが、物事には踏むべき手順というものがあるのだ。
俺と彼女は話し合ううちにお互いに好意を持った。そのために時間をかけた。
「あの子は優柔不断なのよ」
俺たちはそのことでだけは団結できそうだった。
「八戒」
「はい?」
八戒の態度はどことなく投げやりだ。わざと厳粛な空気を作るまいとしている。生憎今日はそうはいかない。嫌でも結論を出してもらわないと先に行けない。
「まだ姉貴のこと好き?」
八戒は怪訝そうな顔をした。そりゃそうだ。俺は人の傷には触らない主義だ。
「あー…苛々する」
開いた間を埋めるべく彼女が呻いたが、俺は無視した。
「そうかもしれませんね」
八戒は握ってきたオニギリを石の前に置き、もう一個を俺に差し出したりしながら、どうでもよさそうに言った。そうかもしれないが、それじゃ困るのだ。俺たちは腹をくくってきているのに張本人ひとりが呑気にされては、彼女じゃなくても憤るというものだ。
彼女が最初に現れたのは先月だったか。信じてもらえないかもしれないが、夜中にドアを開けて入ってきた。そしてひとりのんびり晩酌中の俺に向かって喚いた。
「二股かけてるわよ、あの子!」
あの子というのが八戒のことで、二股というのが俺と彼女のことだと分かるまで、しばらく時間がかかった。俺は慌てて彼女に茶を出し、彼女は勢いよく飲み干した。
「なんで私がここにいるかというと、あの子がまだ私を好きだからよ」
「結構じゃねえか」
「でも貴方のことも好きなのよ」
「そりゃ初耳だ」
「困るのよ」
俺は別に困らなかったが、彼女は八戒の傍にいつまでも引き留められていてはそれはもう困るのだ。一途に思い続けてくれるなら八戒の命が尽きるまで守ってやってもいいがそうじゃないなら何の義理がある、崖から落ちようが馬に蹴られようが知るもんか、私はさっさと成仏するからあんたが面倒みろ、私には私の人生があるのだと言い募った。俺はその口上を非常に好ましく思った。まったくそのとおりだ。
あの子という言い方は、俺をうっとりさせた。彼女が女として八戒を好きでいながら姉としても好きである、というその微妙なラインも、俺には実に素敵に響いた。恋愛小説のようではないか。
俺がうっとりしていると、彼女は俺を張り倒した。
「人ごとじゃない!」
そうだった。
「はっきり聞くが」
俺は彼女と八戒の両方に言った。どうも一番損な役割を引き当てた気がしないでもないが、まあいつものことだ。
「おまえは俺のことを、姉貴より好きだったりするのかね」
八戒の手からオニギリが落ちた。三角だったそれはコロコロと芝生の上を転がり丸くなって止まった。
「僕が悟浄を?」
「そう」
俺が寝てる時に、こいつが俺に時々することを、知らない訳じゃなかった。
ただ俺は、もっとゆっくりでいいと思った。多分八戒もそうだっただろう。
でもそれは、俺たちの理屈だった。彼女はずっとそれを見ていたのだ。ずっと。
我々は八戒のどんな些細な反応も見逃すまいと食い入るように見詰めたが、八戒は無表情に遙か先のオニギリを見ている。晴れた空を雀が横切って、鳴いた。
「…そんなに気になるなら拾ってきてあげようか!?」
緊張に耐えかねて彼女が余計なことを言ったが、少なからずその声は上擦っていた。
俺は彼女の手を握りたかった。助け合いたかった。どんなにか、そうしたかった。
八戒はいつまでも黙っていた。ほっておくと地球が滅亡するまでそうしていそうだった。
勿論俺と彼女は地球が滅亡するまで付き合う気はなかった。
もう充分だ。
この石ころの前で返事ができない返事であることで、もう充分返事になっている。
彼女は「お疲れさま」と俺に言い、弟の額に別れのキスをした。
そして俺に手招きしたので、俺も同じところにした。
八戒は目を見開いたと思ったら、そのままずるずると倒れた。構ってられるか。俺と八戒にはこれからいくらでも時間があるのだ。
「結局この子が一番得したのかしら」
彼女はそう言ってから「いい男二人に挟まれた私も得だわ」と独り言のように言って、余韻のへったくれもなく消え失せた。あっという間もなかった。
得なのは俺だ。
彼女は最後まで、俺自身が八戒をどう思ってるのか聞かなかった。それは彼女のプライドだった。ほんとに生きてるうちに一発やりたかった。あんな女と八戒に同時に会っていたら、俺だって地球が滅亡するまで黙っていたかもしれない。
俺の足下に寝転がった八戒が、いきなりくすくす笑い出した。
「なんだよ」
「…勿体ない」
この野郎は二股かけてる自覚があったのか。美味しいとこどりしやがって。
こういう子なのよ。
俺は怒鳴るかわりに八戒に彼女の名前を尋ねた。
八戒は泣き終わったばかりのような笑顔で、その綺麗な名前を教えてくれた。
fin
花喃(言い張る)。
宇宙蒸発の花喃と同じ人(言い張る)。
悟浄と花喃が付き合っちゃえばいいんだ。八戒はお兄ちゃんって呼ばれればいいんだ。
雪葉様にはもう申し訳なさすぎて慰謝料とか払いたいぐらいです。
泣く悟浄+笑う八戒。
■BACK