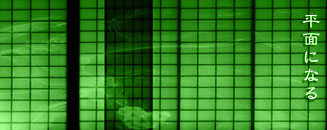
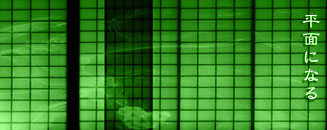
■BACK
悟浄は型どおりの遊民で、これといって住処が決まっている訳でもなく、気が向くと八戒の間借りへやってきて、しばらく居着いたと思ったらふっと消え、見ないと思った頃に現れる、近所の鴉のようにふらふらした男だった。
体が続くうちはいいがいつまでも若い訳じゃなし、そんな適当な生活で先行き不安はないのかと友人らしく意見もしたが、そんな心のこもらない忠告を見抜けないほど馬鹿な男でもなかった。
八戒は老舗宿屋に養子に出た跡継で、生活に不安もない代わりに道を踏み外すこともできない不自由な身の上だったので、その日暮らしの男を羨ましく思う気持ちがないでもないのだ。
「踏み外す度胸がないだけだろうに」
忠告から始まる会話は、常に八戒が憮然として黙り、悟浄が笑って終わった。
さて八戒は近頃悩み事を抱えており、そのせいか気が浮ついて、帳簿を付け誤る程だった。
商売人が帳簿の数字を間違えるということは、医者が切る手足を間違えるのに等しい。加えて一刻前に申しつけられた言伝をすっかり忘れ、書類を廊下に撒き散らし、挙げ句の果てには慣れきったはずの作業手順を違えて同僚と軽い諍いを起こした。
八戒はたちどころに失態を隠蔽したが、自分で隠蔽しておきながら根が真面目なのでますます気鬱になり、気位が高いこともあって他人に事を相談できず、もっとも気位が地の底を這っていたところで簡単に話せるような話でもなく、気が付くとただひとりの友人である悟浄にはこちらから連絡する手だてはない。
淡泊極まりない悟浄が(でなければ逗留先の幾つかは教えていくだろうから)事態を解決してくれる見込みなどまるでないのだが、彼さえいれば即座に気鬱を、例え束の間でも晴らせてくれるはずだった。遊民の取り柄などそれぐらいのものだ。悟浄が八戒を宿の当てにするように、八戒は悟浄の効能を当てにした。だがもう翌晩には短気にも痺れをきらし、いっそこのまま憂鬱を抱えて死んでしまおうとまで思い詰め、発作的に窓枠に手をかけたその途端、計ったように下で手を振る人影が見えた。
「……悟浄?」
「飛び降りか?ちょっと待て、下がるから」
悟浄は本当に数歩下がって顔を上げ「眼鏡ははずせ、死に顔を傷つけるといけない、その前に借金をチャラにする旨証文を書け」などと延々と往来でわめき立てるので、八戒は近所中の見せ物になる前にさっさと身投げを諦めた。
悟浄が裏口から部屋に上ってくる間に、悟浄に金を貸した事など一度もないわ、どうせ潰れる顔に傷もないわで、八戒は思わず微笑さえした。
あの男、あれでも少しは慌てたのだ。
「死んだと思って言えないことはねえだろ」
悟浄はいつものように酒を注ぎ、のんびりと煙管に火を点けた。
「言えよ」
「…言って、貴方に居心地悪く思われるのが、どうも」
悟浄は腕の中の座布団をぽんと叩いた。起きている時も寝る時もしっかり抱いているせいで悟浄専用の枕に成り下がった座布団のくたびれ具合は、彼がここに入り浸って過ごした日の数をはっきりと示しているようで、八戒には悟浄の言わんとしていることが分かった。
そこで八戒は座り直し、座布団に向かって神妙に言った。
「姉がいるんです」
「兄じゃなく」
「姉です」
「素敵だ」
悟浄は座布団を抱いたまま、しばらく身動ぎしなかった。
「…いっこう居心地は悪くないようだが」
「ここにいるんです」
「うわ」
悟浄は飛び上がるように立ち上がり、それでも座布団は離さないまま押入から天井まで覗けるところは全部覗いてまわり、もう一度「うわ」と言った。
「念のため尋ねるが、その、おそらく美貌であろう姉上はご存命なのかな?」
「生憎先立ちました」
「だと思った」
人生を悔いる調子で唸ったと思ったら次の瞬間すとんと腰を下ろし、悟浄は常に八戒に眩暈を起こさせる、極彩色の破片が飛び散ったような不思議な色の目をいっそうキラキラさせて身を乗り出した。
「それで?」
「…何が?」
「どんなだ?丑三つ時に枕元に座るようなつつましい感じか?布団を剥いで触ってくるような情熱的な感じか?それとも物陰から視線を送ってくるような初々しい感じか?それとも」
「姉だと言いましたが」
「女だろ?」
姉が鏡や硝子に映り込むのだ。自分かと思ったら姉である。面差しは昔から似ていたが、そもそもが男と女なのだから見間違うほどではない。見詰めていると、自分は動いていないのに向こうが動いて物を言うのである。
「なんて?」
「それはちょっと」
悟浄は乗り出した身を元に戻した。
「…あのよ八戒、そこは肝心要な部分だと思うんだが。怪談にとりたてて造詣が深いわけじゃねぇが忠告ならひとまず聞くべきだし願事なら叶えてやらねえと。それともあれか?姉上は何やら無理難題を言うのか?顔が良くて気性が悪い女は逆より遙かに酷ぇぞ」
人様の身内に随分な物言いだ。
八戒はしばらく着物の裾を握ったまま逡巡していたが「その前に」と呟いた。
「貴方には懇意…というか、将来を誓い合ったような方がいますか」
「いる訳ねえだろ」
「そう願っているといった程度でもいいんですが」
「ああ、その程度でいいんなら」
悟浄は煙を吐きだした。
「おまえかな」
悟浄の背後に貼り付いていた姉が、はっきりと喋った。
は な れ て
六畳間にたっぷり煙が充満するまでの短くもない間を悟浄は軽く首を傾げたまま黙り続け、八戒は間を埋めるべく酒を啜り続けた。視界が歪んできた頃に、悟浄は不意に顔を上げた。
「姉上を手籠めたことは?」
「…何?ですって?」
「俺は悪い友人か?暴力を振るったり金品巻き上げたりするような?」
八戒はのろのろと首を振った。
「いい人とは思えませんが。いい友人です」
「なら嫉妬だ。俺がおまえとこうして仲睦まじく酒を酌み交わすのにも我慢ならねえという訳だ」
「…確かに姉とは色々とありました。でもよくよく考えてみれば彼女が貴方に嫉妬するのも妙だし」
「何故?」
「何故って…僕と貴方に同じ将来なんて有る訳がないでしょう」
悟浄の軽口を笑い飛ばすべく八戒は微笑みながらそれを言ったのだが、悟浄はくすりとも笑わなかった。
「成る程」
突然、何か大変な失敗をしでかしたのではという思いで八戒は真っ青になった。
悟浄が気分を害して、得意の気まぐれでふいと部屋を出てしまい、懇意にしている逗留先から自分の部屋を外してしまって二度と訪れなくなる事は、八戒にとってまさに恐怖だった。体が震えることで、それが分かった。
「悟浄、あの」
「何?」
声音だけは酷く甘ったるいが、一旦怯えだした八戒の震えはますます酷くなり、手から猪口が転がり落ちた。濡れた指が頼りなく畳の縁をなぞり、辿り着いた悟浄の着物の裾を掴んだ。
「悟浄」
悟浄は裾に酒が染みこむのも構わず、瞬く間に八戒が八戒でなくなっていくのを眺め続けた。気位の高いこの男が、口では友人などと称しながらはっきり人を見下していた腹立たしいこの男が、必死で自分の顔色を窺って媚びてくるのを。
そもそも悟浄は物の怪の類など頭から信じていなかった。かといって作り事にしては出来が悪すぎた。八戒のことは八戒が思うよりよく知っていた。橋を往き来する黒山の人だかりから選んで呼び止めたのは悟浄なのだ。鴉も止まる木は吟味する。八戒が八戒ならぐずぐずと悩みに入る前に打てる手はすべて打ってくるはずだった。身投げするにしても綿密に計画を練らずには済まない、四隅を合わせなければ紙も折れない男だった。
もう跡形もない。
「…なぁ八戒。その姉貴とやらは」
「もうその話はいいです。貴方が嫌ならもう。だから」
「いつ何処に見える?」
…“見える”?
「…貴方がいると…この部屋に」
悟浄が部屋にいると、煙の向こうで姉が言うのだ。
離れて。
離れろ。
早く。
…そうだ。
悟浄が連れてくるのだ。
甘ったるい煙と、妙に苦い酒と一緒に、悟浄が。
極彩色に飛び散る破片。奇妙な色の空。懐かしい姉の夢。
書類を廊下に撒き散らした指の痺れも、記憶を千切れ飛ばしたあの風も、すべて悟浄が。
とっくに気付いていて、しかしもう待たずにはいられなかったのだ。気鬱を払う代償にこつこつと削り取られ、ほんの僅か残った自分の正気が硝子に映り、一番に望んだ姿で叫んでいたのに。
---何です、それは。
---薬だ。夢を見る薬。望みの夢が見られる。
八戒に悟浄の他に友人がいないのは生来からのことではなかった。悟浄がいい顔をしないから、悟浄がいつ何時訪ねてくるか分からないから、自然と部屋に他人を入れず、気軽に外出もできず、そうやって少しずつこうなった。
「あの手合いは骨までしゃぶる。一番いけないのに目を付けられた」
「おおかたひとりで地獄に堕ちるのが寂しいんだろうよ。害虫ほど仲間を欲しがるもんだ」
周囲の雑音など既に耳に入らない。悟浄は自分から何も毟り取ったりしない。ただ与えてくれるだけ。悟浄に教わるまで酒にも煙草にも縁がなかった体に一滴、墨を流したように毒のまわりは早かった。
「おまえに夢に見るほどの女がいたなんてなぁ。面白くはねえが、まあいい。たかが夢だ」
悟浄はゆらりと立ち上がって灯りを落とした。
今や悟浄だけでなく畳も天井も輪郭が溶けて、虫の巣のように赤く蠢いて見える。
「おいで親友。予定より少し早いが今のうち、お望み通り出してやる。足腰が立たなくなっちまったら、道を踏み外しようがねえだろう?」
…悟浄はおかしな事ばかり言う。きっと放蕩が過ぎて頭がどうかしてしまったのだ。だからあれほど言ったのに。自分はどこにも行けないし、行く気もない。道を踏み外すこともない。遊民などとは違うのだ。自分には寸分の狂いもなく決まった人生がある。規則正しい生活と決まった住まいと仕事がある。
…あったはず。
耳朶に押しつけられた冷たい唇が、耳ごと舐め溶かすように囁いた。
「もう帳簿なんかできねえよ。その頭じゃ」
さて、名をなんと言っただろう、あれは。
気鬱も誇りも一緒くたに食い散らかして奈落の底まで引きずり込んだ、あれの名前は。
目を焼いたのは髪ではなくあれを燻す炎で、甘ったるいのは声音ではなく悟浄が吐くあれの煙で、あの時必死で縋り付いたのは悟浄ではなくあれだったかもしれないが、どちらにしても同じことだ。無くては耐えられないのだから。
上も下も、昼も夜も、快も不快も、今や生と死すらたいした違いはないのだし、あれの名だってもしかしたら悟浄だったかもしれない。
悟浄に愛されたか憎まれたかしたのだ。
酷く。
fin