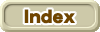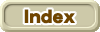
これはなんの因果か、急に思い立ち、必要でもない初級シスアドの資格を取ろうと血迷った
ある間抜けな男の話である。合格までに何度も挫折を乗り越え、そして栄光の合格証書を
勝ち取る、涙なくしして読むことの出来ない感動の実話なのである!
第1話 事の始め
だいたいこの「初級シスアド」とは何か?ご存じない方も多いので、あえて解説しましょう。
正式名称は「情報処理技術者試験・初級システムアドミニストレータ」というものなのだ!
これはれっきとしたコンピューターの国家資格の一つなのだ!ちゃんと通産省がやっている
コンピューター関係の資格で、内容は「EUC推進のための資格」という位置づけになっている。
EUC(=End User Computing)エンド・ユーザー・コンピューティング、つまりプログラマとか
開発者側ではなく、使う側、つまりユーザー側から見たコンピューター推進係というような立場の
資格なのだ。もちろんこの情報処理技術者試験というのは、開発者側の「情報二種」とか「一種」
その他「ネットワーク」関係など色々ある。で、この初級シスアドというのは、その情報処理
技術者の第一段階の資格みたいなものなのだ。だから簡単だろうと思ったのが、それがそもそもの
間違いだった。
1999年の7月のとある日曜日。たまたま本屋でコンピューター関係の雑誌を立ち読みしていた。
すると「これからはコンピューター関係の資格が必須!」の記事を見かけた。なるほどねぇ、
これから我々公務員の教員もリストラされる時代にはいるだろうなぁ、何か資格あった方がその時の
ためにはいいかなぁ..などとぼんやり考えていた。それはたんなるぼーっとした考えだったが
それよりもなによりも、最近の自分って、何か一生懸命やっている時ってあんまりないよなぁという
漠然とした思いだった。もちろん仕事では手は抜いていないし一生懸命やっている。でもその学校の
仕事としてだけの能力なんてたかがしれている。もっと個人として何か前向きに取り組むことが
ないなぁと考えていた時期だったのだ。別に資格を取るなんて事は考えていなかった。ただ何か
もっと日々充実して何かに向かっているという充実感が欲しかったのだ。そこでこの資格が目に
付いたのだ。何でも良かったのだが、何か自分が満足できて、しかもお金がかからなくて、時間が
なくてもできて、そして意味あるもの。形が残るもの。そんな自分を向上させてくれるような
都合の良いものがないかなぁ(^^;)と考えていた矢先だったのだ。
そうか...コンピューターの資格かぁ...それなら多分少しは出来そうだし役に立つかもしれ
ない。勉強も暇な時を見つけて少しずつやれば負担にならないし、何より資格が取れるし...。
なんて安易な気持ちで始めたのが運の尽きだったのだ。でも善は急げというから、さっそく
コンピューター関係の資格はどんなものがあるのかと色々調べてみると、あるわあるわ50近く。
ワープロ検定からP検、マルチメディア検定と呼ばれるもの、国家資格からメーカ認定もの、全然
聞いたこともないようなマルチまがいのものまで。ふーん、色々あるんだ。でもどうせやるなら
公的なものの方がいいなぁ。そうすれば箔がつくし(つくか?)やっぱ国家資格でしょ。えーと
情報一種、二種、ネットワークスペシャリスト、上級システムアドミニストレータ...色々
あるなぁ。で、受かりそうなのは...(笑)そうだ、実際の問題を見て、ちょこっと勉強すれば
受かりそうなヤツにしよう。どれどれ、情報一種...うっ!なんじゃこりゃあ...ははっ、
一種なんてね...じゃあ、二種はと...えっ!?プログラミング?そんなやったことないし..
ネットワーク...もう知らない言葉だらけで、まるで宇宙語。こんなに難しかったのか..
恐るべし、情報処理技術者試験!実はこの時点で、もう無理だ。やっぱり止めようと思っていた
のだ。どう考えても独学で出来そうにもないし。でもここで諦めるのもなんか悔しいなぁと思って
初級シスアドの問題集を見たとき『おおっ!これならわかる!』と思った問題があったのである。
そうか...これならできそうじゃん。名称もシステムアドミニストレータとか言って、長くて
かっこいいし(笑)えっ、これって解答が四択なの?なら楽勝じゃん。...驚くなかれ、こんな
安易な決断で、この資格獲得物語が始まったのである。げに恐ろしや、素人は。実際はとても難しく
合格率も3割程度と意外に低く、たまたま私が出来た問題も偶然の産物だったのだ。しかしすっかり
やる気になって、意気揚々ととりあえず問題集を買って帰る私だったのだ。ああ、ここからが地獄(笑)
第2話 知れば知るほど
とりあえず「合格情報処理」という雑誌を買ってきて、詳しい内容を確認するところから始まった。
しかし自分で言うのも何だが、この時になって初めて、このシスアドっていうもんを知ったのですよ。
それまでは何となく簡単そうだというイメージだけで決めてしまったけど、ここで初めて色々なことを
知ったのです。例えば試験は年に2回あり、春(4月)と秋(11月)だとか、試験は午前と午後の
2つに分けて、それぞれ2時間半もあるとか...もうびっくり!でもまぁ、この時点ではまだ余裕で
何とかなると思っていたのですよ。で、この雑誌を見ると、申込書が付いている。というか受験料の
郵便振替が願書代わりなんだけど、よーく見ると応募が早いほうが希望受験地が近くなるとか出ている。
こりゃ早い方が良いということで、その日のうちに郵便局へ。善は急げですから(^^;)
で、家に帰ってもう少し詳しく読んでいくと...えっ?計算問題があるの?何、表計算ソフトの
問題も?データベース?SQLって?どんどんわからない言葉と問題が出てきた。えーっ?午後の
問題って、こんな長文読解みたいで実務をやっていないと全くわかんないようなものばかりじゃない!
もう驚きましたよ、マジで。あまりに無謀なことだったと。なめたらいかん初級シスアド。ああ、もう
受験料振り込んじゃった...(泣)5100円も...。こんな難しい問題解けるわけないじゃん。
本屋で立ち読みして解けた問題は、たまたま簡単で奇跡的に知っていたことだったのか...。だって
出てくる専門用語の7割ぐらいは知らないし、これではとても無理。そして何よりも驚いてのは
合格率。3割程度しか合格してないの!?6割ぐらいかと思ってた...(泣)もうだめだ。
あきらめよう。無理無理素人には。それぐらい難しく感じましたよ。
でもここで能天気な私。でも待てよ。これってマークシートで四択だよなぁ。もしかして偶然で
出来るかも...。なんてまた安易なことを考えてしまったのです。昔からマークシートというか
勘はいいからなぁ(笑)えーと、午前中の問題は全部で80問。どれくらいで合格なのかなぁ...。
えっ?7割ぐらいは最低欲しいって?じゃあ80問の7割って...56問正解?ここに書いてある
過去の午前中問題80問で、ぱっと見て自信を持って答えがわかったのが....9問!あといくら
勘が良くても47問も当たるわきゃない...ダメだ。いくら四択の勘がいいからって...えっ?
午後の問題は四択じゃないの?えー!中には15ぐらいの選択肢から選べとか、10ぐらいの選択肢
から2つ選べとか...そんなの当たるわけないじゃん!(完璧に勘頼り(^^;))こうなると正解する
確率なんて天文学的確率になってしまう....。うーむ、こう見ると午後の問題で点数を取るのは
奇跡に近いなぁ。それに午後の問題は表計算ソフトやデータベース関係の問題ばかりだし、その上
実務関係(実際の会社の業務、例えば受注発注量・経理関係等々)で、私には全然無縁。だから
この問題は何をしようとして、何を求めているのかもちんぷんかんぷん。ほとんど一問も出来そうに
ない。こうなったら丸暗記で午前中の問題を完璧にして、午後を捨てるしか道はないなと
悟ったのです。
しかしこの時点では午前午後とも足切りがあり、それぞれ6割程度越えていないと、どちらかが
パーフェクトでも、合格できないとは知らなかったのだ...恐るべし、無知の私!
この時点で、秋の試験日まであと4ヶ月足らず...。どうするO−TEACHER!
第3話 基本の基本の基本の言葉
そんなわけでいよいよ学習開始である。まず私が一番最初に適当に買ったのが、テキスト形式の
参考書だった。「イラスト図解でよくわかる合格読本」みたいな本だった。今思えば、初心者で全然
わからないにしては比較的良いテキストを選んだ。でもである。これがまた全然わからないのだ。
何がかって?全部である(笑)とりあえずイラストと数は多いのだが、それが何を意味しているのかが
よくわからないのだ。そもそもその言葉がよくわからないのだ。例えばこんな感じ。ウォーター
フォール式システム開発、CAM、DFD、ERモデル、KJ法、QC七つ道具、ABC分析、
チェックディジット、ブラックボックステスト、レグレッションテスト、公開鍵暗号方式、SQL、
正規化等々。ねっ?わからない人にはわからないでしょ?(笑)いくら考えても、私が10年ぐらい
コンピューターを扱ってきたけど、こんな不可思議な言葉たちには全然出会いもしなかった。なんじゃ
これは?お前たちはどこの言葉じゃ?ってな感じだった。実はこの時点ですでに挫折しかかって
いたのだ。『やっぱりこんな通産省が認めているような国家資格は、お堅いだけだ。こんなもん
実際のコンピューター使う現場の知識とはかけ離れている!無駄だ無駄だ!』と一人憤慨して
いたのだ(今考えるとただ、わからないから怒ってただけのような気が(^^;))
でももう受験料を振り込んでしまった。このまま無駄にするのも悔しい。少しは身につけねば
無駄銭となる。とりあえずやれるところからやりますか。ということで、わからないと文句ばかり
言っていても仕方ないので、虚心坦懐、学ばせていただきますという、素直な気持ちで学習に
取り組むことにした。まずは一番最初の、わからない言葉をチェックして理解するところから
始めた。そしてそれをひとつひとつしらみつぶしに片付けることを当面の目標に置いた。幸い
月刊合格情報処理の付録に、コンピューター用語辞典なるものが付いていて、これを参考に調べて
いった。しかしである。コンピューターの言葉は難しすぎる。それはいくら調べても分かり
切らないからである。例えばこんな感じのこと。「ウォーターファール式システム開発」という
言葉を調べたとする。するとこんな感じで書いてあった。「システム開発形式の一つ。
ウォーターフォール=流れる滝 のように開発工程を段階的に進める方式。システム部が主導と
なる。ユーザ側のフィードバックはしにくい。途中単体テストを行いモジュール結合をしていく。
その他の方式にプロトタイピング式、スパイラル型などがある。」これって素人が一読して
わかる?こんなの日本語じゃないよね?国語の教員として怒りまくりですよ。それでよく意味が
わからなくて、この言葉の意味を知るために、また単体テストとかモジュールとか、プロト
タイピングとか調べる。するとまたそこに訳の分からない言葉の羅列...。もう本当に投げ
出したくなりましたよ。こんな基本的な言葉の意味すら分からないのに、ましてそれについて
応用したような問題が解けるわけはない。基本の基本がわからないまま7月が過ぎていきました。
どうする!?O−TEACHER!
第4話 都合のいい確率
さていよいよ1999年の8月。私たち先生にとっては嬉しい夏休み(あっ!生徒に
とってか!?(笑))しかし勉強の前には休みなどないのだ。ということでこの頃から本格的に
勉強し始めた。だいぶ試験の内容がつかめてきたのもこの頃。そうかシスアドって、プログラマー
とかの試験じゃなくて、ユーザー側のコンピューター資格なのね...って、今頃気づいて
どうする!本当にお気楽でしたよ、私は。それでも何となく勉強しなければいけないことが
見えてきた(これも遅すぎるっちゅうの)基幹業務システムに関してとかシステム環境整備とか
運用管理、エンドユーザコンピューティング...言葉は難しいけど、実務的な知識から応用まで
初級とかいうから簡単かと思ったら全然そんなことはない。これは数学的な知識(だって確率や
標準偏差も出る)から計算問題(稼働率やデータ処理計算等)まで、はたまた著作権、プレゼン、
最新技術、表計算、データベース等々、こんなに幅広く出るとは思わなかったのだ。うーむ、
とりあえず、なんとなく出てくるらしき言葉はピックアップしたから(もちろん意味は分から
ないもの多数)まずは午前問題80問を試しにやってみることにした。
またこれがとても難しい。ブレーンストーミング?検収書?バケット交換?デジョンテーブル?
いくら四択だといっても、まず言葉の意味からやらねば...。えーと次の文の中から、ブレーン
ストーミングを表しているものはどれか?えーと、えーと、まず第1問目から答えが「ア」って
ことはないな。普通「イ」か「ウ」でしょう(笑)なんとなく「イ」っぽいなぁ...えーと
解答は...ほら、やっぱり「イ」だった。俺って勘がいい!(笑)こんなんじゃ受かるわけ
ないですね、マジで。とりあえず解答の解説を読んで理解するか...えーっと、「ア」は
OJTについての文章、「ウ」はロールプレイング、「エ」はPlan-Do-Seeである。よって答えは
「イ」....って全然わからん!なんじゃOJTって?これからしてわからん!ロール
プレイング?ドラクエやFFなら全部やってるけど、役割劇のこと?「エ」に至っては英語の
ことわざか?
こんな感じでほとんどお手上げである。一問理解するために、付随する解説や間違った選択肢の
内容理解。そしてそれがすべてわかった上で、はじめてどこが間違いで、どこが合致しているのかを
確認する。よって一問理解するのに半日かかってしまうのだ。ということは、午前問題だけで
80問。一日2問として40日。夏休みが終わってしまう(泣)全然無理。それも半日調べまくって
わかればいいけど、あとで気が付いたのだが、答えが見つからないものも多い。また解説が
見つかっても、それがどういうときに使われるのか、どんな場合の言葉なのか、想像ができない
ものも沢山あって、完全に理解したとは言い難いのだ。そのため全然自分の中に知識として蓄積
しない。だからしばらくすると忘れてしまって、再度同じ問題をやってもできない...悪循環。
えーい、もうこんなことやめだやめだ!どうせ四択だ!なんとか勘で当ててやる。明らかな
間違いはひとつぐらい見つけられるから、そうすれば三択。1/3の確率。80問なら26問
ぐらい当たる計算。確実にわかる問題が20問ぐらいあって、あとは偶然が重なれば7割ぐらい
できるでしょう。はははっ。これで合格さ。軽いもんだ。へへん。...とここまでは楽天的では
なかったけど、けっこう近かったかも(^^;)というより、勘を頼りにするしかないぐらい、実は
わからなくて困っていたのです。うーむ、この額から出る汗は決して冷や汗ではなく、単なる
暑さのせいだよね...(^^;)ちょっと投げやりが入ってきたO−TEACHERでした。
第5話 午後は無理無理
そうこうしているうちに9月!試験日は10月の第3日曜日。あと一ヶ月ほど。でも学校が
始まってしまえば、忙しくて勉強している暇はない。相変わらず適当な勘と生半可な知識だけで
わかった気になって、午前問題80問をこなしていた。そしてこの時期になってやっと午後問題に
取りかかり始めたのだ。なんという遅さ!今考えると冷や汗というか苦笑い。この午後問題と
いうのが実にくせ者。これが実は今後、足を大きく引っ張ることになるとはこの時はあまり考えて
いなかったのだ。で、この午後問題も150分。つまり2時間半。こんなに長い試験時間なんて
必要だろうか?と思っていたのですが、必要です(笑)実際は全然足りないのだ。その内容だが
午前問題の四択とは全然違い、すべて長文の問題。大きな問題が7問ぐらいあり、その中に小さい
設問が4〜6問ぐらいあるのだ。それが難しい難しい。すべて実務系の問題なのだ。どの問題も
ある会社の特定の業務を例にして問題を作ってあるのだ。例えばある商社の取引先とのことに
ついて問題が出ている。商品台帳に関するデータベース問題。Aという商品が、5000円以上で
在庫がいくつで販売実績がどれくらいで...と、まず現状について長々と1ページ分、
約800字程度説明してある。だからまず仕事の業務内容を理解し、その会社の商品管理の流れを
理解し、そしてここでは何が問題かを理解し、そしてやっとその上でどうしていくか改善点が
問題となるのだ。読解力はもちろん、実務的な知識がないとほとんどわからないのだ。こりゃあ
学生の合格率が低いわけだ。だから私も読み始めても何を書いてあるのかほとんど理解不可能。
このデータをE−R図で表記すると?営業販売実績を月次取引実績で抽出しろ?取引先コードの
結合とは?これを表計算ソフトに入力したときI4(セル番地)に入る式は?等々。全滅です。
だいたい、こんな実務寄りの問題、こういう会社勤めの人じゃなきゃわかるわけないじゃない
ですか。私みたいにぽーっと教員になった人間なんか、こんなの全然わからない。もちろん学生
にも。そして何よりも困ったのは四択じゃなくなったこと。選択肢が10個ぐらいあって、
その中から1つだったり、場合によっては2つ選べとか...。もうこうなると天文学的な勘の
良さが要求される。模範解答を見て愕然!80問中正解がたった6問!ある意味ここまではずす
のは逆に勘がいいかも(^^;)こんな直前になって、実は一番ショックを受けていたのです。そして
こういう長文問題はじっくり時間をかけ、内容をよーく頭に入れてやらなければ出来ないのに、
仕事に忙しく、ゆっくり熟考する時間無し。たった10分の休み時間では問題文も読み切れま
せんって。ああ、こんなことなら夏休み中に午後問題をやっておくんだったと後悔。もうとことん
追いつめられました。ピーンチ、O−TEACHER!
第6話 運命の日
そんな何も準備もできないまま迎えた試験の日。実はとても用意周到な私は、一週間前に
試験会場へ下見へ出かけたのだ。日曜日で天気も良くちょっとしたピクニック気分で。自宅から
約1時間。会場となった、とある大学は駅から徒歩25分。けっこうあったけど、下見をして
なんとなく雰囲気をつかんだ。あとラスト一週間頑張るのみと決意を固めた。この頃は本当に
ラストスパートの勉強。実は知り合いのとある情報処理系の専門学校の先生に、その学校で使って
いるシスアドの予想問題プリントをもらい(^^;)わずかな暇を見つけては勉強していたのだ。
小さなメモにして、まるで受験生のように片時もはなさず問題を見ていた。職員会議にまで持ち
込んで(さすがに会議中は見なかったけど(^^;))
そしていよいよ当日。会場へ行ってびっくり、とても沢山の人。まぁ、情報二種の人も受ける
から多いのは多いんだけど、それにしても意外と沢山の人がいてちょっと気後れ。それと
若い人が多いのも驚いた。情報処理系の専門学校生や大学生が多数受験しているためらしい。
でも自分の受ける部屋へ入ったら、意外と年輩の人も多くちょっと安心。でもいかにもこの
資格がないとリストラされそう...という雰囲気を醸し出している年輩のおじさんも多く、
ちょっと気圧され気味。でもこれだけ冷静に観察する余裕もけっこうあった(^^;)
さていよいよ試験。午前の部スタート!9時半から12時までの長丁場。運命の四択スタート。
事前の下調べで、このシスアドの午前問題は、過去の問題が多少アレンジされて出る傾向が
あることを知った。確かに同じようなことを聞いて、選択肢だけ違う問題、計算問題も数値を
変えてあるだけで、同じものを要求する問題。そういうものが目に付いた。だから解きながら
『あれ?この問題、見たことがある!』と思うやつが何問かあった。しかしやりながら気づいた
こと。それはあやふやな知識のままで、完全に覚えきっていない、理解していなかったという
ことだ。解きながら何となくは思い出すんだけど、『あれ?これってどっちのことだっけ?』と
思うことがとても多かった。何となくは覚えているのに確信を持って答えられないもどかしさ。
うーん、見たことあるのに...。そんな感じで、いかに勉強したことが定着していなかった
かを痛感。もっと確実に覚えておけば...(泣)そうこうしているうちに午前の部終了。
放心状態。
そして最大の試練午後の部。これは問題を一通り目を通した瞬間『やばい...一問も
わからない...』と気も失わんばかり。マジで全然わからなかった。E−R図、SQLの
データベーススキーマ。ソフトウェアのライセンス契約の許諾条件に関する問題。ファイル
サーバの障害対策とバックアップに関する問題(RAID5やらDATやら)CD貸出業務の
データ管理とDFDについて。表計算ソフトを使った万年カレンダーの計算式。販売管理
データベースの様々なSQL...。ひとつも...いえ、謙遜でなく、本当に、ひとつも
わからなかった。目の前真っ白状態。すべて勘。それでもけっこう悪あがきして、何とか文意に
ヒントが書かれていないか読み込むが、無理。ほとんど全滅状態。最後の方の高配点の問題まで
ほとんど手が回らず。2時間半も試験時間があるのに、7問中5問を何とか終えたところで、
あと30分!もう愕然。あとは問題も読まずにただ勘と、マークのばらつき具合のバランス
だけ考えて、マークシートを塗る(笑)だってマークシートを塗るだけで時間が足りない
もので。そしてラストの小問を塗り終わったところでラスト1分半!そして見返すまもなく
終了。またまた放心。どうやって帰ってきたかわからず。
自分で自分が情けなくなった。こんなにできないなんて。間違えるならまだしも、どういう
やり方で解いたらいいのかがわからなかった。例えば因数分解の問題が出ているのに、
覚えているピタゴラスの定理でなんとか解こうとしているような感じだった。使うのは
これじゃないってわかっているのに、それしか覚えていなかった、そういう気分だったのだ。
中には何を聞かれているか全くわからない問題もあり、すごい嫌悪感。あんな勉強で受かろう
なんて、なめていた...。猛省。
そして夜、インターネットで解答速報を見て自己採点。100点に換算して、午前72点、午後
62点。つまり午前7割、午後6割。合格確実は午前午後とも8割。絶望。60点以下は
足切りもあるという噂...。こうして茫然自失して、世の中は甘くないと、身をもって
実感した一日でした。マジで夜、眠れなかった。どうする、O−TEACHER!
第7話 結果分析
色々なシスアド関係のホームページを見ると、問題の解説が載っているものを見かけるように
なってきた。そして答え合わせをすればするほど泣きたい気分になった。解答速報でやった
点数より悪いのだ。7割6割ならもしかして...という淡い希望もあったのだが、始めより
あと10点ほど低い感じ。情報処理関係の雑誌などを見ると、予想合格ラインが、午前午後の
合計で142点と出ていた。私の場合、134点ぐらい...。やはり無理か。でももしか
したら...って万に一つの可能性ぐらいを期待していた。そしてその後、シスアド関係の
掲示板で見かけた、様々な人の感想や解説。どれも今だからわかる本音と解説。こんなに
真剣にやっている人がいたんだから、あんな適当な勉強で受かるなんて虫が良すぎる。そう
実感しました。そして冷静に結果分析すると、やはり過去に出てきた問題の刷り直しを多数
発見。過去問さえちゃんとやっておけば...悔やまれる。そして何より痛かったのは計算
問題が全然できていなかったこと。稼働率の問題、解像度の計算、画像伝送時間の問題等々。
単位を間違えていたり、ビットやバイトのことがうろ覚えだったりと、やっぱり身について
いなかったと実感。ああ、ショック。やっぱり無理だったのか...。絶望しつつ納得でき
ない一ヶ月でした。
第8話 朗報!?
様々なシスアド関連のホームページで気になっていたのだが、午後の問題の解答が一部違う
ところがあった。確かに主催者は正解を発表していないので、本当のことはわからないが、
だいたい普通に答えを考えれば同じになるはず。ところが午後の、ある大問が、どこを見ても
大きく2種類の答えに分かれている。そんなにちゃんとした答えが出ない問題なのだろうか?
それとも難しい問題だったのだろうか?実は私には全然わからない問題だったもので(^^;)
そうこうするうちに、とある掲示板で、あの問題はおかしい、ミスがある。誤問だという指摘が
書かれていた。表計算を使って万年カレンダーを求める問題だと思ったのだが、私には何が
ミスなのかももちろんわからなかったが、そう言えばあちこちでそんな指摘を見かけたなぁと
思っていた。するとこのことがあちこちで取り沙汰されるようになってきた。とうとう
情報処理系の雑誌にも明らかに誤問と書かれていた。なぜ誤問かというと、どうやら解が2つ
存在するらしい。つまりその2つの答えで、どちらでも正解らしい。また他のページには、この
解き方だと、問題で聞かれている答えが出ないとも書いてあった。何かを求めるための式が
あって、そこに当てはまる数値や記号を入れていくのだが、その式自体が間違えているらしい。
だからどんな数値や記号を入れても正解は出ないらしい。ふーむ、そうなのか。じゃあ正解が
ないんじゃどうなるんだろう?とぼーっと思っていた。
するとなんと公式発表があった。なんとそれはやはり明らかな出題側のミスらしく、そこの
問題は、解答に関わらず全員得点を与えると発表があったのだ!えーっ!マジで?だってそこの
問題は全くわからなくて、全部適当に書いて、全部見当違いな答えを書いて全滅したところ
だよ!それが全部得点になるの?超ラッキー!もしやもしや...もしかして?計算し直すと
15点ぐらいUP!これはもしかしたら...。淡い期待を持ってしまったO−TEACHER
であった。でもこの時点では全員が得点するのだから、平均点が上がるだけで合格率には関係が
ないとは全然気づかなかったのだ。
第9話 当然の帰結
そしてとうとう合格発表の日。この合格発表だが、直前にならないといつかわからないと
いうのがすごい。確かに官報に載って初めて決定だから、その掲載日が決まらないと正式な
合格とならない。その載る日は、急ぎの公示事項があるとそちらが優先され、後になることも
多いためとか。それでも発表までに1ヶ月半も待たせるとは、何のためのマークシートなのか。
それでもいよいよ発表日が決まり、それがホームページで掲載されることとなった。午前0時に
出るらしいが、その瞬間は混み合うらしく激重らしいので、朝見ることにした。でも前の晩は
ドキドキしてよく寝付けなかった。私って小心者なのね(笑)
そして朝、いよいよ閲覧!えーと、えーと、ここだ!えーと私の受験番号は...上4桁は..
これこれ、そして下の桁の方は..........ない。何度見てもない。何度も確認するが
やっぱりない。まっ、当然の帰結だろうけどやっぱりない。ショック!これが現実の厳しさか。
底上げの加点があってもやっぱりダメだったか...。実は期待しない期待しないと言いつつも
もしかして?とほのかな期待をしていたのだが、淡い夢、露と消える。悔しい。でも仕方ない
とも思う。あんな中途半端な勉強で受かっていたら他の人たちに申し訳ない。そんなに甘い
試験ではないと痛感した。でもショックが隠しきれずその日一日ブルー。終日ぼーっと過ごす。
何の気力も湧かない。今後どうしよう。やっぱり無理だからもうあきらめようか...でも
今までやった勉強が無駄になるのも悔しい。でもまた一から勉強をする気力もない。
どうしよう。あきらめるのか?仕事も忙しいし無理か?心の葛藤がせめぎ合う一ヶ月。
第10話 メルマガで再起!
そんな傷心の私を慰めてくれるものがあった。それはシスアド関係のメルマガ。メールマガジン
です。少し前から購読していたのですが、実は問題集ばかりやっていたので、あまり目を通して
いなかったのです。しかしここに来て、そのメールマガジンを何気なく見てみると、それ関係の
ホームページが載っている。そこへアクセスして掲示板等を見てみると、いるわいるわ同じように
落ちた人が(^^;)ああ、自分だけじゃないんだ。みんなショックを受けて落ち込んでいるんだ。
そしてまた次に受けようとやる気を出している人も多いんだ。そう気づいたのです。中には4回も
5回も落ちている人もいる。たった1回落ちたぐらいで...ちょっと恥ずかしくなり反省。
せっかくここまでやったのだから、もう開き直ってライフワークにしてやる!そう決意したのです。
そして何よりも励みになったのは、このホームページの掲示板によく書き込んでくれる
”まさよさん”感謝してます。本当に慰められました。ありがとう。
そう思って再び勉強しようという熱意が戻ってくると、意外と冷静にやれるようになった。まず
敗因分析ということで、いったい何がまずかったか客観的に考えた。ひとつは覚えた気になって
実は正確にわかっていないことがたくさんあったということ。これはもう一度全てノートに書き出し
ひとつひとつ調べて書き込むところからやり直そうと決意。そして2つ目は継続性の問題。仕事の
忙しさ関係もあるが、継続して勉強できなかったこと。一日ずっとやったかと思うと、三日ぐらい
何もしないこともあった。これではいけない。わずか10分でもいいから、一日一問でもいいから
継続的にやらなければ力にならないと痛感。そこで役だったのはメルマガ!今までほとんどちゃんと
見ていなかったけど、これならわずかな時間目を通すだけで済む。2つほど購読していたのを毎日
きちんと読むように心がける。実はこれが一番実力UPに役立ったと言える。そして3つ目は午後
対策。これは内容理解を始め、時間配分等々全然ダメだったので、これにまず力を入れることを
決意。でも実際に午後問題って、勉強の仕方が難しいのだ。過去問やっても、数回やっているうちに
だいたいわかってしまうし、かと言ってそんなに問題集があるわけではないし...。だから
とりあえずは過去問の完全理解。そして予想問題集の読破。そして表計算とSQLを飽きるほどやる。
そういう勉強体制を確立していったのだ。メルマガによって再度トライしようと決めたのだ。
第11話 正しい勉強法
そうと決めたらひたすら勉強。合格ノートなるものを再度作成。うろ覚えの言葉を抜き出し、
解説を書いていく。書くことにより覚えていない点が明確になってきた。そこから出てきたわからない
点は、必ず同じページに書き込む癖を付けた。そうすれば後で見返したときに、連想して覚えられる。
そしてメールマガジンによるシスアド問題は、読むだけでわかった気になってしまうので、面倒でも
必ずプリントアウトして、チェックするようにした。マーカーで重要箇所もチェック。最後の方には
これを1ページ1問にして綴じ、高校生の単語帳のようにして、暇なときにペラペラめくって読める
ようにした。これなら時間がないときでも継続して勉強できた。そして最大の問題であった午後対策は
やはりこれだけは頼るものが少なく、とりあえず月刊合格情報処理を熟読。そして掲示板などで
良いと評判のあった問題集を買ってきて、例題集を徹底的にやる。これをやるときには必ずExcelを
使い、実際に式をたててみて、なぜそうなるのか、どうしてこの式なのか、納得するまでやってみた。
だから午後問題をやるときはコンピューター前でソフトを使いながらやる。SQLにしてもそんな
感じ。こういう勉強法でやりきった。何が正しい勉強法か人によって違うと思うけど、自分にとって
このやり方が、一番時間を無駄なく使えた勉強法だと思う。さて受験料も払い込み、あとは再度
チャレンジするのみ!